【役員インタビュー】昭和産業 山口龍也取締役常務執行役員、業務用は課題解決力磨き、家庭用は3本柱で需要喚起図る
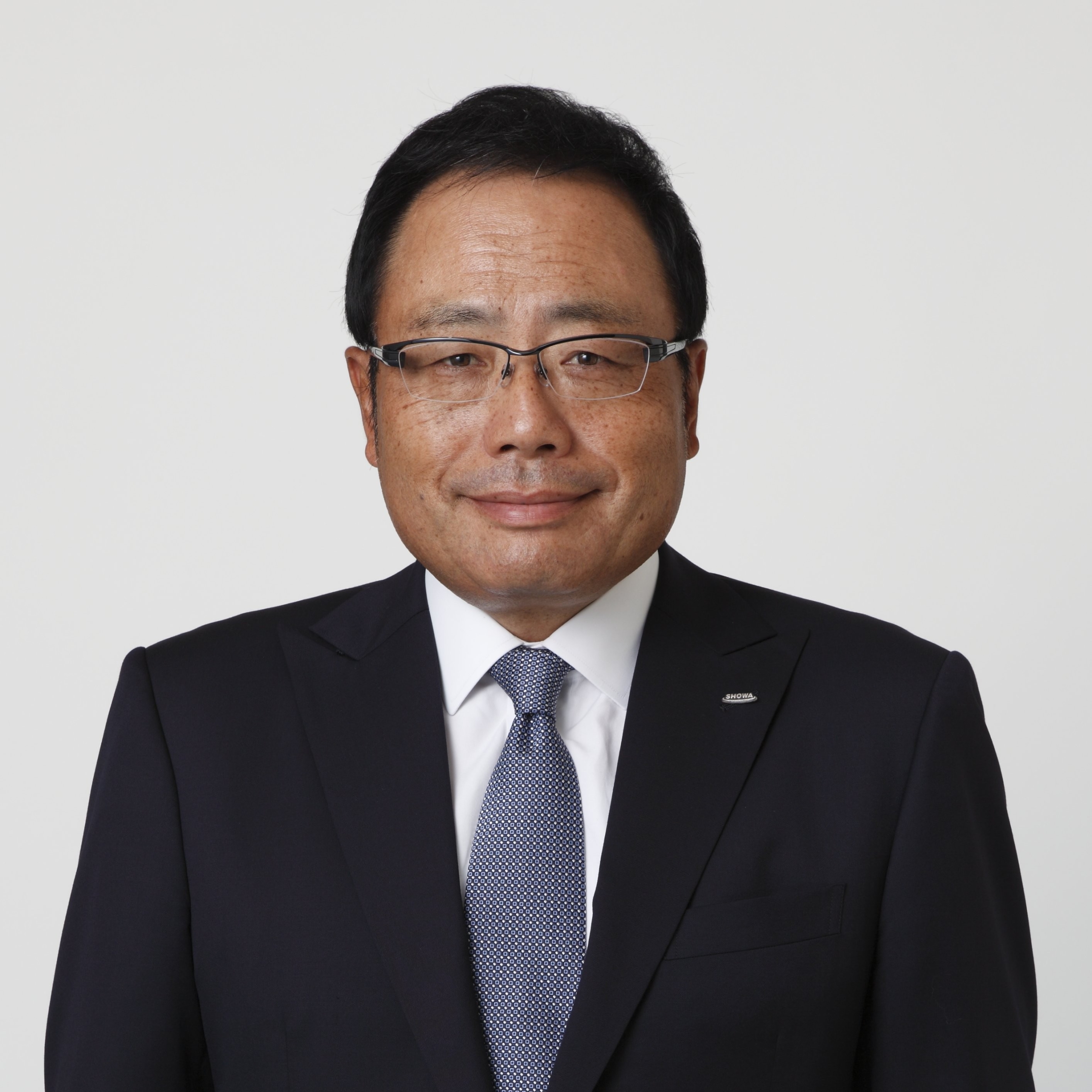
◆油脂販売で想定していない用途への展開、新商品も現場の悩みの解消を目的に開発
――油脂の環境の総括を
2024年度は油脂業界のコスト環境は非常に悪化した。主要原料の大豆・菜種相場が軟調で推移していたが、為替は年間通して円安基調が継続し、原料価格高止まりの要因となっている。加えてこの1~2年、食品業界全般で生じている大きな採算悪化要因が、エネルギーコストや資材・包材費、輸送費、人件費などあらゆる経費、費用の上昇だ。原料相場や為替はさまざまな要因で変動するが、物流費や人件費は今後も下がることは考えられない。
このような環境で2024年10月に価格改定を発表したが、3月末時点で当社が要望する水準までは届いていない。収益は前年度から大きく減少する厳しい結果となり、油脂事業は減収減益だった。
業務用の販売は、インバウンド需要の拡大もあり順調に推移している。コロナ前の水準には達していないが需要は回復基調にある。ただ、家庭用は汎用油が前年並みだったものの、大幅な価格改定を行ったオリーブ油の減少の影響が大きく、物量的には苦戦している。
――価格改定の浸透状況は
原料以外のコストが大きく上がっている。2024年10月の価格改定が3月末時点では求める水準まで届いていないということで、4月からさらに20%の値上げをお願いしている。顧客の中には昨年10月からの価格改定を発表する直前に相場が下がったことで、相殺されるのではないかと捉えられた例もある。今回は取り巻く環境について、より丁寧に説明し理解を求めていく。
――業務用の取り組みを
組織改編を行い、丸2年経った。油脂の販売でもソリューション営業によって販売先の広がり、想定していない用途への展開が出てきている。例えば、昨年も多くの新規採用があったが、製菓・製パンなど、小麦粉のユーザーで新たに油脂製品が採用されたのが印象的だった。
組織改編前においては、これらのユーザーにとって当社は製粉メーカーの位置づけのため、小麦粉の細やかな提案はできていたが、油脂の提案力は薄かったと感じられる。組織改編によって、小麦粉と同様に油脂や糖質を提案できるようになった。小麦粉だけでは解決できなかったユーザーの課題を、油や糖質の切り口によって解決できるようになったのは1つの進歩だ。
その解決提案の過程で元々想定していなかった使い方が採用された例もある。麺のほぐし用途で開発された油脂を和菓子の生地に練り込むことで食感改良をもたらした例や、フライ用途で開発された油脂をバッター生地に添加することで、衣のサクサク感を向上させた例も出てきている。こういった提案はこれまでの営業スタイルでは生まれなかった。
新商品についても、より現場の悩みの解消を目的に開発を進めている。昨年の新商品「フライオイルCK‐UP」は、フライヤー周りの油汚れを気にする、現場のパート社員の声をもとに開発した商品だ。炊飯油「こめコート」は米を炊いた後、チルドや冷凍で流通、保管していると、米が老化してパサつきや風味低減が気になるという声を受けて開発した。今後もマーケットから生まれてきた要望や不満の声を大切にし、商品や提案をブラッシュアップしながら課題解決力を磨いていきたい。
◆家庭用は物量回復のための需要喚起、オリーブ油・オレインリッチ・こめ油の3本柱で
――家庭用については
家庭用は金額ベースでは2024年度も過去最高水準となっているが、これはオリーブ油を中心にした油脂の価格が値上がりしているためだ。消費者の価格に対する防衛意識もあり、物量的には厳しい。今期は汎用油の適正価格浸透が大前提だが、オリーブ油を中心とした物量回復のための需要喚起が重要だと考えている。オリーブ油、「オレインリッチ」、こめ油の3本柱で家庭用を組み立てていく。
オリーブ油はスペインの2年連続の歴史的不作の影響で高騰していたが、生産量は回復してきている。元の価格には戻らないかもしれないが、昨年、一昨年のような手の届かない価格ではなくなっている。健康面とおいしさを再提案し、販売を強化していきたい。昨年は世界中で取り合いになったので、まずは安定量を確保することから始める。
プレミアム油の中で伸長が続いているこめ油は家庭用で200億円市場が見えてきている。グループのボーソー油脂、当社の商品ともに期待している。こめ油のヘルシーさ、唯一の国産原料の油という切り口で消費者ニーズを喚起できるようにしたい。
ひまわり油の「オレインリッチ」はオレイン酸が80%入っているということが消費者にも評価されており、さらに拡販していきたい。昨年はオリーブ油が価格高騰したことを受けて「オレインリッチ」とのブレンド油を発売したが、オレイン酸の含有量はオリーブ油と変わらない。他メーカーとは違う切り口で継続して販売していく。
〈大豆油糧日報 4月30日付〉








