第71回通常総会、新会長に長谷川健太郎専務理事が就任/納豆連
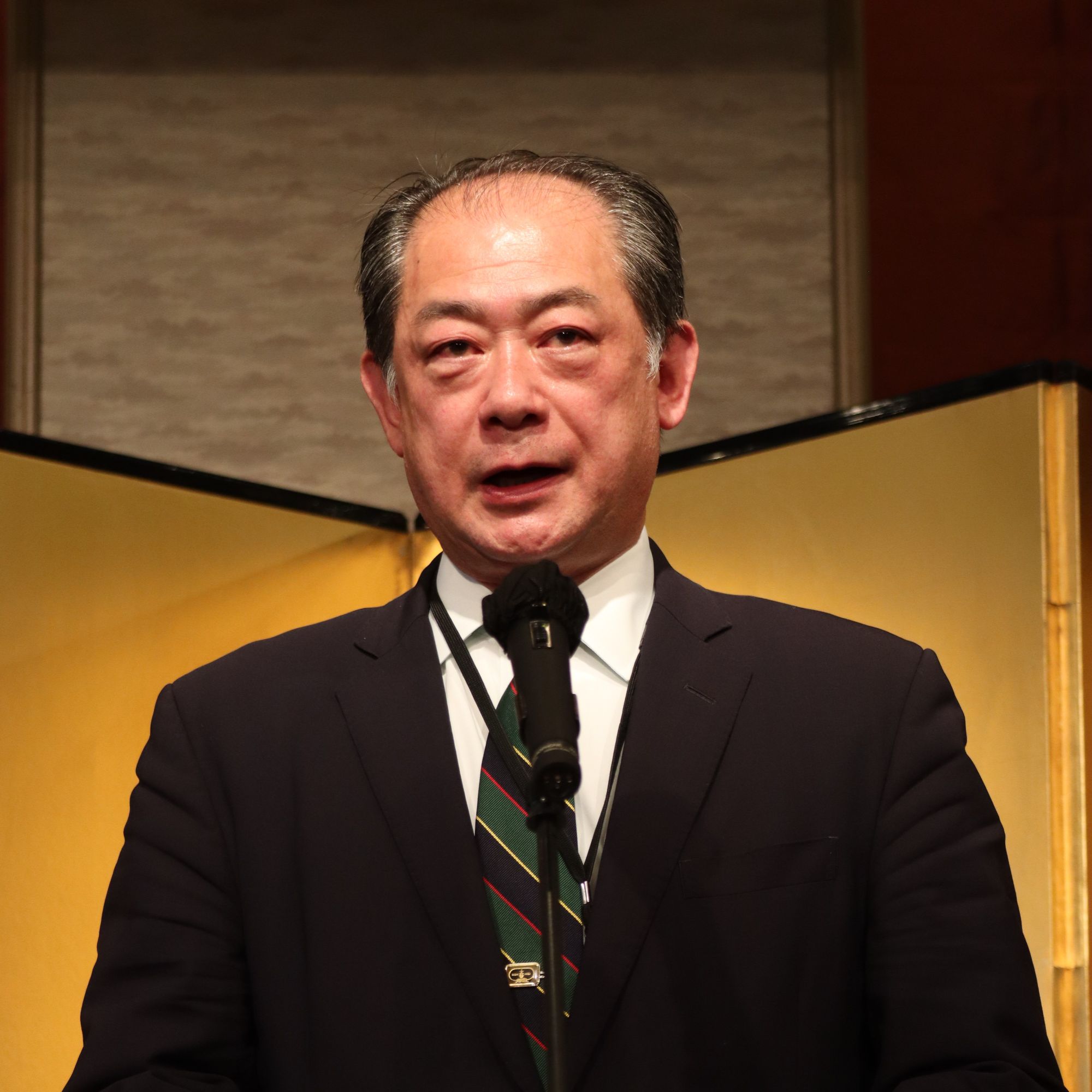
全国納豆協同組合連合会(納豆連)は5月9日、第71回通常総会を上野精養軒で開催し、令和6年度事業報告、令和7年度事業計画など全議案を承認した。野呂剛弘会長が会長職を退任し、長谷川健太郎専務理事が新会長に就任した。任期満了に伴い理事と監事を選任し、理事として新たに槇亮次氏、村田滋氏、岡田琢磨氏、関本政英氏、工藤裕平氏が就任し、監事として新たに塙秀茂氏が就任、そのほかは再任した。

冒頭、野呂会長があいさつし、「平成9年(1997年)に青年同友会の委員として組合活動に携わって以来、30年間にわたり、業界の発展に微力ながら尽力してきた。12年前の総会において会長職を拝命して以降、コロナ渦や国際情勢の変化、価格転嫁の問題など、業界を取り巻く環境は幾度となく大きな変化に見舞われた。そのたびに、会員の皆さまの団結力と熱意に支えられ、何とかその責務を果たしてくることができた」と述べた。
続けて、「思い返せば、青年同友会の委員として活動した日々は、私にとってかけがえのない貴重な経験となった。同世代の若き経営者と真剣に議論を交わし、胸襟を開いて本音で語り合う関係を築くことができた。こうした信頼関係は、今なお私の支えとなっている」と振り返った。
令和6年度事業報告のうち、納豆連が22年から取り組んでいる輸出事業では、国の補助事業として、組合員を代表してマルキン食品がラスベガスのフードショーに出展し、視察したことに触れた。日本食に親しみのある米国人は、納豆に対する受容性や関心が非常に高いことが明らかになったという。
令和7年度事業計画については、今期はリードタイム2日の実現を目指すとした。これにより、納豆製造の計画生産を可能とし、生産性向上が見込めるという。さらに、フードロスや、効率配送の実現によるエネルギー削減などにも貢献できるとしている。
◆ 「組合の存在意義は、個々の企業では解決できない課題に対して動くこと」
最後に、長谷川新会長があいさつした。「組合員数は減少している。最盛期の昭和38年には858社加盟していたが、現在は100社を下回る。今後も増加は見込めず、業界全体の力が弱まっていく可能性は否めない。だからこそ、今できることを積み重ねていくことが大切だ」と述べた。
続けて、「組合に加入するメリットは何かという問いがあるが、単に所属するだけで恩恵を受ける時代は終わった。現在において組合の存在意義は、個々の企業では解決できない課題に対して、業界全体としての声を発信し、動くことにある」と話した。「やろうとしたことが必ず達成できるわけではないが、やろうとしなければ絶対にできない。行動を起こすことで初めて変化が生まれる」とした。
「また、組合は共助と考える。他の大豆製品の業界を知る人から『納豆業界はよくまとまっている』と言われることが誇らしい。これを維持することが極めて重要だ。時代が変われば必要とされることも変わる。しかし、業界のまとまりは変えてはならないものだ。それこそ組合に加入する最大のメリットだ」と語った。
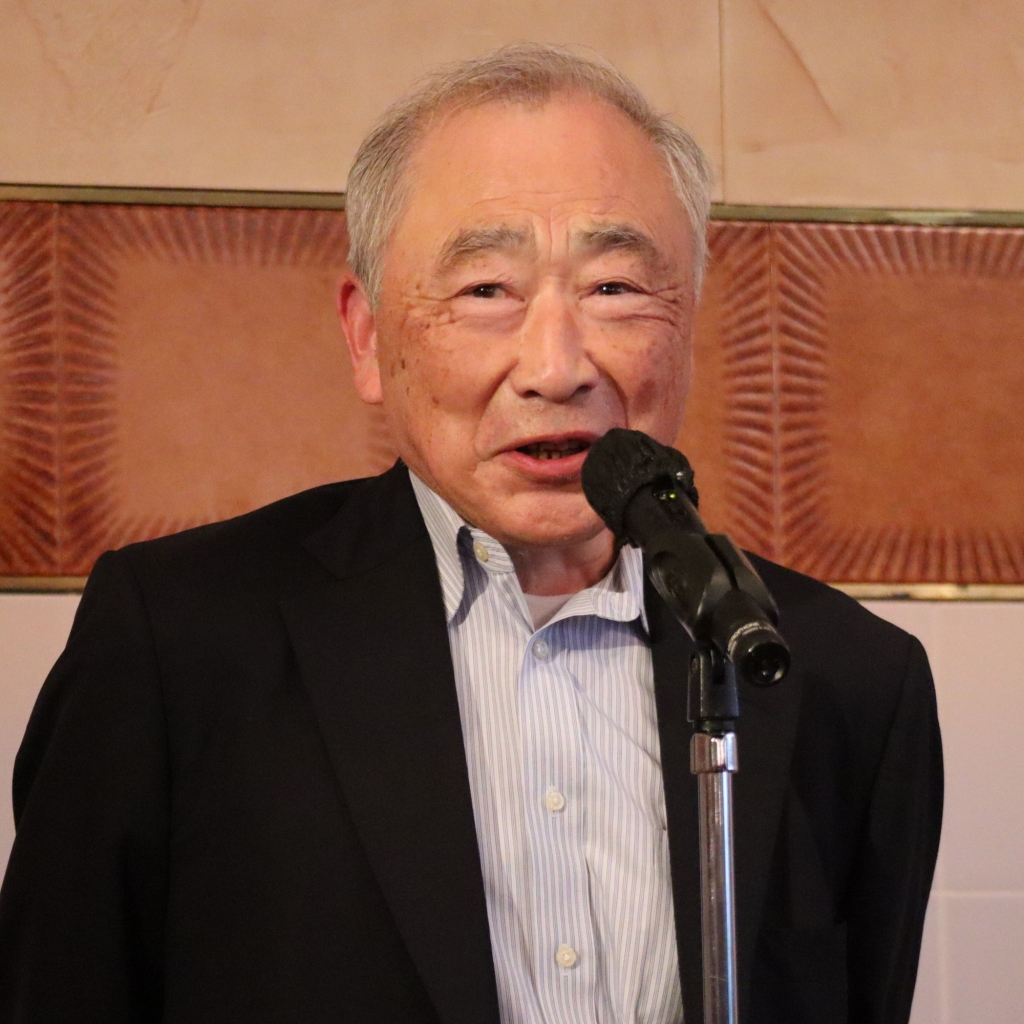
総会後に開催された懇親会では、今期で副会長を退任した工藤茂雄氏があいさつした。「私は日本で一番長く糖尿病を患っているが、肝臓も腎臓も悪くなっていない。幼少期から納豆を食べ続けているので、納豆が症状を抑えてくれたのでは、という想いがずっとあった。納豆こそすごいパワーがあると思う。そのエビデンスが出てきているのも、組合がいろいろなテーマで分析しているからだ。納豆業界ほど、団結してアクションを起こせているところはない。世界の人のためにスーパーフードを賞味できるようにしたい」と話した。
〈大豆油糧日報 5月13日付〉








